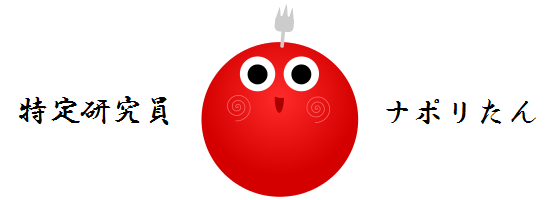題名:二人だけの合図
報告者:ダレナン
本報告書は、基本的にNo.1876の続きであることを、ここで前もってことわりたい。
そこで死んでいたんだ。僕は…。あの時、入水していたら…。「ごめんごめん、仕事遅くなっちゃって…」。
妻が病室に入ってきた。「買ってきたわよ」。渡されたレジ袋の中を確認すると、そこには、ハイネケンではなく、ザ・ブリューが入っていた。
「あれっ、ふぁいねけんはどきょ?」
「病院近くのコンビニによったんだけれども、そこにはなくってさ。まっ、同じようなもんかなとこれ買ってきたの。ねぇ、これでいいでしょ」
「…うん、まひぁ…」
依然の妻なら3件ほどの店を回って「あった、あったわ、ハイネケン。なかなか見つからなくて3件もお店まわちゃった。ダリオくん、これでしょ、これでいいんだよね」と渡してくれた。依然の妻なら。でも、もう、そこにはザ・ブリューしかなかった。ハイネケンじゃない。しかもはっぽーしゅ。違う。これじゃない。妻はザ・ブリューにストローを刺して、僕に差し出した。ちゅうちゅうした。
ぶほっ、喉の奥がトラ・ブリュー。違う。これじゃない。「ほらっ、まだ駄目よ。しばらくよくなるまでお預けね」。妻はそのザ・ブリューを僕の手から奪い取ると、ごくりごくりと飲んだ。「美味しーわ、これ」。
その妻を見て、随分と昔と変わってしまったことを痛感した。時間は着実に色を褪せさせていた。昔は極彩色でも、今は色あせた透明に近い色へと変色していた。色と色の間の区切りももはやなかった。すべての色という色の愛だが、起伏のない平坦な色という色の間へと押し殺されていた。
色の愛、透明で不確実。在っても、無くても、まったく見えない。can this love be true?
その当時、してはならない、という禁忌を意識するあまり、逆にその禁忌の中に自ら踏み込んでいく人間の心理1)が僕には垣間見えた。見えないからこそ怖い。当時、僕に起こったことは誰にも告げてはいない。むろん妻にもだ。クミちゃんもそうだった。でも、告げてはないにせよ妻は気づいていた。きっと彼女のチェンジはそこから始まっていた。隠していても自然と表に出る僕の意識、それは確実に妻にも届いていたのだろう。
「最近、楽しそうね。なんかあったの?」
「いや、特にないけど。たぶん仕事が充実しているんだ」
「ほんとに仕事?」
「う、うん、まあね。今日も遅くなると思う」
「そう、なの? 今晩、ダリオくんの好きなカレー作る予定だけど。クミンたっぷりの。どうする」
「く、くみ…ん…。たたぶん、今日も仕事の関係で、外で食べることになると思う。ごめん」
「ふ~ん」
会社に出向くと受付のプレートには誰にも分からないように右隅に小さなハートマークのシールが貼ってある。それが僕たち二人だけの合図だった。
1) 小池真理子: 冬の伽藍. 講談社. 2002.
…「冬の伽藍」の品への案内は、こちらになります。 地底たる謎の研究室のサイトでも、テキスト版をご確認いただけます。ここをクリックすると記事の題名でサイト内を容易に検索できます。